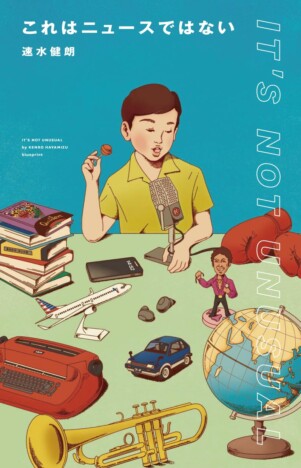ドイツの若き名匠が『消えた声が、その名を呼ぶ』で描く、“隠れた歴史”への壮大なる旅路

今から10年前、英国のミニシアターでとんでもないドイツ映画と出会った。描かれるのはとにかく不器用で、凶暴で、歪(いびつ)な愛。なにしろハンブルクで始まった物語がいつしか国境を越え、イスタンブールにまで導かれていくのだ。この映画にとにかく度肝を抜かれ、すぐさまその担い手、ファティ・アキンについて調べ始めた。73年生まれ。俳優であり映画監督。トルコ系ドイツ人ーー。ベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞したその作品は、1年以上遅れて日本でも『愛より強く』というタイトルで公開された。続く彼の『そして、私たちは愛に帰る』(08)はカンヌ国際映画祭にて脚本賞を受賞。そして『ソウル・キッチン』(11)では、ヴェネツィア国際映画祭審査員特別賞を受賞。つまり彼は30代の若さでベルリン、カンヌ、ヴェネツィアにて名を馳せる存在となったわけだ。
そんな彼が、かつてない製作規模にて最新作を完成させた。それが『消えた声が、その名を呼ぶ』である。本作は<愛><死><悪>というテーマを扱った3部作の最終章という位置付けらしい。つまり<悪>についての物語。蓋を開けてみて、そのスケール、テーマ性、映画作家としての凄まじい執念に打ちのめされた。

物語の始まりは今から100年前のオスマン・トルコ。少数派のアルメニア人として生きる主人公ナザレットは、第一次大戦が始まるや兵士に連行されて強制労働に従事させられる。愛する妻や娘たちのことを想いながら、過酷な労働を耐え抜く毎日。力尽きた者が次々に倒れていく。そんな中で突如、殺戮が始まる。砂漠の真ん中で処刑人たちに首を切られ一団は虐殺されてしまうのである。このアルメニア人の虐殺に関しては犠牲者が100万とも150万とも言われており、のちにヒトラーがこの一連の流れをユダヤ人の虐殺の手本にしたとの説もあるほどだ。
本作の原題は“The Cut”という。主人公も他のアルメニア人と同様、首に刃を突き刺される。だが、処刑人は良心の呵責に苛まれて彼を絶命させることができず、密かに手当を施して彼を逃してくれる。彼は一命を取り留めた。ただし、その代わりに声を失った。また、愛する妻や娘たちは彼が不在のうちにどこか別の場所へ強制連行されてしまったらしい。引き裂かれる家族。民族。ナザレットにとって家族は最後の希望だった。彼は広大な砂漠地帯をさまよい、家族の消息を尋ね続けるのだがーー。

声を失う主人公は、虐殺の被害者たちの声なき声を象徴する存在と言える。前半部は虐殺までの道のりをあくまでナザレットの目線で描き続ける。そこまでの顛末もかなり衝撃的なのだが、そういった告発のみに止まることなく、いかにそれらを盛り込んで「物語」を形作るかが本作の一番の焦点。その意味で、むしろ圧倒されるのは後半部だ。そういえば、まだ平和だった頃の故郷で、主人公ナザレットと双子の娘たちは空を鶴が飛んでいくのを目にする。「あの鳥を見たものは、長い長い旅をする」。そこで交わされるセリフの通り、本作では想像を絶するほど壮大な旅が観客の心を翻弄し、鷲掴みにしていくのだ。